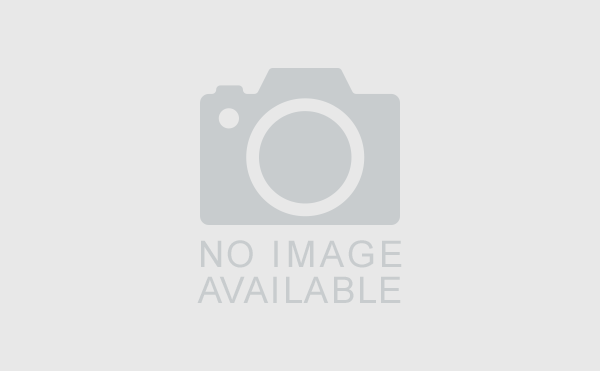年越しそばご予約プレゼント「御宝銭」
昨年年越しそばセットにお付けした「福寿銭」はお客様から「宝くじが当たった」など御利益のご報告を多数いただきました。中には「おすそわけ」とプレゼントをお送りくださったお客様もいらっしゃいました。そうしたお客様のお声をいただき金運向上が望まれるようでしたのでお調べしたところ、金運向上の神様として知られる真岡の「白蛇神社」へ行ってまいりました。
白蛇弁財天で皆様の幸せと金運向上をお祈りし御神水でお金をお浄めしてまいりました。
さらにそのコインを持って「大前恵比寿神社」もお参りしてまいりました。
「年越しそば」をご予約いただいたお客様に真岡白蛇弁財天でお浄めした「御宝銭」をプレゼントします。「年越しそば予約ページ」からお申し込み下さい。銀行振込をお選びいただいたお客様は26日迄にお振込をお願いします。26日迄にお振込の確認ができない場合はキャンセル扱いとなりますので予めご了承下さい。
プレゼントは年越しそばと一緒にお届します。

年越しそばの由来や年越し蕎麦の意味、などは以前ブログにも掲載しましたが江戸発祥の神事で、大晦日にお召し上がりいただく蕎麦は特別な縁起物です。
「御宝銭」は数に限りがございますのでお早めに「年越しそばセット」をご予約下さい。